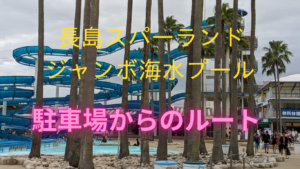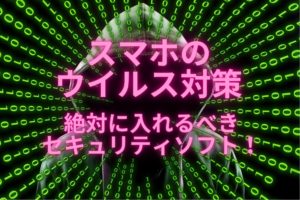おはようございます.ぐ~ままです.
今日(2021年9月23日)は,「秋分の節気」です.
季節感が薄れてきている今こそ,二十四節気の季節感を見直したいと思います.
この記事の目次
秋分の節気
「二十四節気」の16番目の節気になります.
太陽黄経は180度.
太陽が真東からのぼり,真西に沈むため,昼夜の長さが同じになる日.
この日を境に,徐々に昼間が短く,夜が長くなります.
また,この日を境に,太陽は赤道より南側に移動するため,日本(北半球)から遠ざかり冬に向かいます.
秋分の日は,なぜ祝日か?
日本では,「秋分の日」 は祝日ですが,なぜだかご存じでしょうか?
「秋分の日」「春分の日」が祝日なのに,なぜ,「夏至」「冬至」は祝日じゃないのか,と思った人はいませんか?
はい,実はぐ~ままはずっと不思議で仕方がありませんでした.
「国民の祝日に関する法律」 を調べてみると,「秋分の日」 は,「祖先をうやまい,なくなった人々をしのぶ」 日となっています.
つまり,昼と夜の長さが同じ,真ん中の節気だからという理由で休みなのではなく, 「祖先をうやまい,なくなった人々をしのぶ」 というちゃんとした理由があるのです.
そしてこれは,もともと秋分の日に,宮中で歴代の天皇や皇族の神霊をまつる儀式が行われていたことに由来するそうです.
ちなみに,秋分の日は,太陽の位置によって決まります.
9月23日が圧倒的に多いのですが,9月22日や9月24日の年もあります.
去年は9月22日でした.
このように,国民の祝日が太陽の位置によって変わり,天文台の発表により決まるのは,世界的にみても珍しいそうです.
秋分の歳時記

秋分,春分の前後3日間,合計7日間は,「彼岸」と呼ばれます.
このころに咲く赤い花は,「ヒガンバナ」として知られていますね.
先祖を供養する日なので,お墓参りなどをする人も多いと思います.
お供え物の「おはぎ」は,秋の七草の「萩」に由来しているそうです.
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言われます.
厳しい残暑もようやく一息つけるといったところでしょうか.
(ぐ~まま)